「・・天下無双とはただの言葉じゃ
天下無双とはなどと考えれば考えるほど
見よう見ようと目を凝らすほど答えは見えなくなる
見つめても見えないなら目を閉じよ
どうじゃお前は無限じゃろう?・・」
(井上雄彦, 吉川英治: バガボンド, 11巻, 講談社, 2001)
天下無双を目指し、数々の剣豪を倒しつつあった宮本武蔵だが、
次第に自分が何故天下無双を目指すのかわからなくなる。
それでも、最強と謳われた剣豪、柳生石舟斎にたどり着く。
すでに年老い、床に伏せたままの石舟斎に手も足も出ない武蔵は、天下無双とは何かを尋ねた。
僕らは言葉の意味に囚われやすい。
そして、囚われることから逆に問いを作ってしまうことがある。
しかし、僕らが言葉を使うとき、いちいち意味を明確に挙げ連ねるわけではない。
意味のようなもの、その言葉の質感を抱いて言葉をただ発するだけだ。
質感-クオリア-は、人それぞれによって異なり決して共有などできない。
しかし、だからこそ、齟齬が生成され、そのことが言葉を使いつづけたり、
会話という相互作用を発展させたり、新しい言葉を作ったり、
新しい人間関係を築いたりする原動力となる。
複雑系科学とはなにか、という問いを大げさに考える必要はない。
僕らは個々にその言葉に対する質感を持っている。
僕たちがこの問いに出会ったとき、その質感をただ表明することに何の躊躇がいるだろう。
「・・鼻歌でEASY ACTION 横目でBYE BYE
悪いけどEASY ACTIONかまわずやらせてもらうぜ・・」
(The Street Sliders: EASY ACTION, In: BAD INFLUENCE, Epic Sony, 1987)
飢餓や紛争とは奇跡的に無縁なこの国で、
EASY ACTION でないことは、おそらく罪であろう。
垂れ流されるだけの情報、複雑に絡み合うことだけに嬉々とする
ネットワーク社会に囚われて立ち止まっている場合ではない。
|
僕が複雑系科学に抱く質感は、自然の得体の知れなさを知るという行為、である。 |
|
僕が幼稚園児のときの、ある日のお絵かきの時間、
晴れた空を描こうとしたところ、青のクレヨンがなかった。
そこで近くの友達に「青のクレヨン貸して」と頼んだところ、その子は緑のクレヨンを差し出した。
もくもくと自分のお絵かきを続ける友達の作業をそれ以上中断できなかった僕は、
緑色で空を塗って、先生に提出した。
時間の最後に先生が一人一人の絵を皆に見せながら評してくれたが、僕の絵に対して先生は、
「なんてきれいな空でしょう」と述べ、そしてクラスの友達は拍手をした。
自分がいつから言葉を使えるようになったか、覚えているだろうか。
僕は、空の色は青に特定されないことを知ったそのとき、言葉という自由な存在を明確に知った。
それは同時に、因果律の不思議、あるいは奇跡、危うさを知るきっかけでもあった。
僕とは違って妻の場合、少々つらい思いをしている。
彼女が小学生のときのある国語の時間、「詩を書いてくるように」との宿題が出された。
あくる日の授業開始のとき、先生は詩の書かれたノートを回収したが、僕の妻の詩を見るや、
「バカにしているのか」と一喝し、頭を張った。妻はなぜ自分が叱られたのかわからず当惑した。
妻のノートには、ひらがなの「し」がびっしり並んでいた。
このように、因果律の成立には、成立のための文脈の共有が必要なようだ。
しかし、個別的な質感を持つ僕たち人間に文脈の共有を望んでも無理である。
だから、因果律の成立ほど、得体の知れないものはない。
ここで挙げられたような文脈共有の不可能性は、僕や妻が子供だったこととは関係がない。
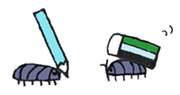
僕の先輩Sさんのエピソードは面白い。
彼は大学に入るまで数学は理解できなかったが、
大学で解析学を学んだとたん数学がわかるようになったという猛者である。
また、将棋の有段者でもある。
そんな彼が大学院修士課程の卒業に当たり就職活動をしていたとき、有名なH製作所の面接で、
「ところで、君はどんなコンピュータで仕事をしているのか」と聞かれた。
面接官は、機種や仕様を聞くことで、彼の計算機に対する知識を図ろうとしたのだろう。
しかし、彼の答えは、「ええっと、白いプラスチックの、
(手で四角を作りながら)こんな感じの箱で・・カタッ、カタッと言うてます・・」であった。
そんな彼は、最も競争の激しい中央研究所に配属され、良い仕事を行った。
文脈の非共有性から生じる因果律の不成立は、一見単なる齟齬の生成であるが、
どうやら新たな可能性を生み出す作用を持つようだ。妻の詩の例も例外ではない。
「詩を5秒で書かなければ命はない」と言われれば、「し」の並んだ詩は、命を助けるかもしれない。
文脈の非共有性は、他人同士の相互作用によってのみ現れるものでもない。
心と体は常に協調し、自分という一つのシステムを構成しているようだが、他人同士になる危うさを孕んでいる。

再び幼少の頃の話になってしまうが、3歳のある日、
友達の家の玄関を開けると、廊下の先に木製の薬箱が置かれていた。
その箱を見た瞬間、僕の目前には、僕が走り出し、
その箱に躓き、頭を打ち、出血するという光景がありありと広がった。
今のは何事だ、と思った瞬間、体は勝手に走り出し、本当に躓き頭から出血してしまった。
出血したことよりも、心から離れた体が勝手に走り出し、
体が躓く様子をコマ送りの映像を眺めるかのようにただ傍観せざるを得なかった感覚のほうに、
恐怖を感じ、人間の得体の知れなさを知った。
このような体験はさすがにこれっきりではあるが、
このときなぜ体は心から離れ勝手に動いたのか、さっぱりわからない。
心と体は、それぞれがその時々で独自の文脈を作りながら互いを存在させ、危うい相互作用をしているようだ。
普段協調できていることが、おそらく奇跡である。
その得体の知れない協調の仕組みはどのようなものなのだろうか。
以上のような独自の文脈は、人間だからこそ作られる、のではない。
人間はそもそも物質である。そして、あらゆる物質は独自の文脈を備えている。
科学の基本は、観察対象の様々な性質を測定することである。
|
コンニャクの厚さをノギスで測ったことはあるだろうか。 |
|
この記録された厚さは、寧ろいつ起こるかわからない反発というコンニャクの潜在力を示す値である。
反発する、しないを決めるのは、コンニャクであるとしか言いようが無い。
このように、厚みという一見客観的な値は測定者が無根拠に決定し、
そのことが、コンニャクはいつ反発するか予測できない、という得体の知れなさを生成する。
反発する、しないは、コンニャク自身による環境の同定の仕方、
すなわち、コンニャク独自の文脈によって決められるのだ。
以上のような、観察対象に備わる文脈生成能という得体の知れなさは、僕たちが観察行為をする限り、
コンニャクに限らずいかなる対象にも現れることになる。
僕は、オカダンゴムシの文脈生成能を、
できるだけ建設的な形で実験によって例示することを主な研究テーマにしている。


冒頭に挙げられたThe Street Slidersの歌詞は、次の歌詞に続いている。
「・・世界を変えるなんて出来ない相談だぜ
いつもとびきりROCK'N'ROLL俺たちゃこれだけ・・・」
世界は変えようと思って変えられるほど甘くはない。
けれど、何かしなければ変わらない。
自分の質感を信じることは、少し照れくさいけれど、できないことではない。
複雑系科学は、多分それを許してくれる。
以上、森山 徹,「複雑系科学の質感」(複雑系科学のすすめ, 未来大学出版, 2006年)の一部改訂版


